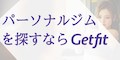国民健康保険税
国民健康保険の加入者に負担していただく保険税についてご案内しています。
国民健康保険に加入すると、世帯主に保険税を負担していただくことになります。また世帯主が職場の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯のだれかが国民健康保険に加入していればその世帯主が納税義務者となります。ただしこの場合の保険税は、実際の加入者本人の分だけです。
保険税は、(1)所得割額、(2)均等割額、(3)平等割額の合計額によって1年分の税額が計算されます。
令和7年度の国民健康保険の税率等を改定します
このため、令和7年度の国民健康保険税の税率等を下表のとおり改定します。
ご加入の皆様が安心して医療のサービスを受けられるよう、国民健康保険の安定的な運営を図っていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
令和7年度の国民健康保険税率と賦課限度額は、国基準に合わせ、改定します。令和7年度の税率は、下記のとおりです。
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.30% | 6.55% | 0.25%増 |
| 均等割 | 25,400円 | 27,300円 | 1,900円増 |
| 平等割 | 23,100円 | 21,000円 | 2,100円元 |
| 賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | 据え置き |
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 2.30% | 2.45% | 0.15%増 |
| 均等割 | 8,900円 | 9,900円 | 1,000円増 |
| 平等割 | 10,300円 | 8,700円 | 1,600円減 |
| 賦課限度額 | 220,000円 | 240,000円 | 20,000円増 |
| 区分 |
令和6年度 |
令和7年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 所得割 |
2.07% |
2.25% |
0.18%増 |
| 均等割 | 9,000円 | 10,600円 | 1,600円増 |
| 平等割 | 8,000円 | 7,000円 | 1,000円減 |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 据え置き |
令和7年度国民健康保険税率
| 区分 | 説明 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分(※1) |
介護納付金分(※2) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 令和6年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)に右記の税率を乗じた額 |
6.55% |
2.45% |
2.25% |
| 均等割額 | 被保険者1人につき右記の額 |
27,300円 |
9,900円 |
10,600円 |
| 平等割額 | 1世帯につき右記の額 |
21,000円 |
8,700円 |
7,000円 |
| 賦課限度額 | 1世帯につき、1年間に賦課される限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
年間国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
※1「後期高齢者支援金分」は0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する保険税です。
※2「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。年度途中で加入・喪失された場合は月割計算されます。
- 年度途中で65歳になる方の介護分については、あらかじめ65歳に到達した月以降の介護分を計算に含めていません。65歳以上(介護第1号被保険者)の方は国民健康保険と切り離して介護保険料をご負担いただくようになるためです。
- 年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、あらかじめ75歳に到達した月以降分を計算に含めていません。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行されるためです。
国民健康保険の計算方法
事例:豊山太郎さんの世帯の場合(4人世帯)
豊山太郎43歳(令和6年中の所得金額400万円)
豊山花子38歳(令和6年中の所得金額100万円)
豊山一郎13歳
豊山二郎10歳
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分(40歳~64歳) |
|---|---|---|---|
| 所得割 |
{(400‐43)+(100‐43)万円} ×6.55%=271,170円 |
{(400‐43)+(100‐43)万円}×2.45%=101,430円 |
(400‐43)万円×2.07%=73,899円 |
| 均等割 | 25,400円×4人=101,600円 |
9,900円×4人=39,600円 |
10,600円×1人=10,600円 |
| 平等割 |
21,000円 |
8,700円 | 7,000円 |
| 合計額 | 401,300円 | 149,700円 | 97,900円 |
令和7年度国民健康保険税=648,900円(年額)
国民健康保険税の納税義務者と納付方法
国民健康保険税を納める方(納税義務者)は、国保加入者のいる世帯の世帯主になります。
国保税の納め方には、普通徴収(納税通知書による納付や口座振替)がありますが、一定額以上の年金を受給している被保険者については、特別徴収(世帯主の年金から天引き)となります。
(1)普通徴収
納税通知書は5月に1期分を、7月に残りの納期分(9期分)をお送りします。
仮徴収
-
5月
- 令和6年度の国民健康保険税額の10分の1の額となります
本徴収
- 7月~3月
- 令和7年度年税額から仮徴収分を差し引いた額となり、残額を9回に分けて納付していただきます。
(2)特別徴収
対象となるのは次の4つの条件すべてに該当する場合です。
新たに該当する方には「国民健康保険税仮徴収額納税通知書」を送付します。なお、既に特別徴収されている方の通知書は日本年金機構の発送する年金振込通知書をもってかえさせていただきます。
- 同一世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 納税義務者である世帯主が国民健康保険被保険者であること。
- 上記の世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
仮徴収
- 4・6・8月
- 令和6年度最後の特別徴収税額(2月の徴収額)と同額を年金天引きします。
本徴収
- 10・12・2月
- 令和7年度年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けて年金天引きします。
※上記4つの条件すべてに該当する場合は、原則として「特別徴収(年金天引き)」となりますが、申請により「口座振替による納付」を選択できます。年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望される方は、預金通帳と通帳届出印をお持ちの上、保険課と金融機関で手続きをしてください。(確実に納付が見込めない方については、口座振替による納付が認められない場合があります。)
国民健康保険税の納期
普通徴収
- 4月
- -
- 5月
- 1期
- 6月
- -
- 7月
- 2期
- 8月
- 3期
- 9月
- 4期
- 10月
- 5期
- 11月
- 6期
- 12月
- 7期
- 1月
- 8期
-
2月
- 9期
- 3月
- 10期
※普通徴収の方の納期限は各月末日ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。
特別徴収
- 4月
- 1期
- 5月
- -
- 6月
- 2期
- 7月
- -
- 8月
- 3期
- 9月
- -
- 10月
- 4期
- 11月
- -
- 12月
- 5期
- 1月
- -
-
2月
- 6期
- 3月
- -
国民健康保険税の軽減制度
(1)軽減制度の概要
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
軽減割合
基準となる所得金額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較)
-
7割軽減
-
世帯の所得の合計額が{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
-
5割軽減
-
世帯の所得の合計額が{43万円+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
-
2割軽減
-
世帯の所得の合計額が{43万円+(56万×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
「擬制世帯主」とは
国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
「特定同一世帯所属者」とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。
世帯の所得の合計額は、世帯主や被保険者等全員の所得を合計したものです。ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行ないます。
譲渡所得は、特別控除前の所得です。
65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
(2)特定世帯について
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
(3)旧被扶養者について
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、所得割はかからず、均等割額は半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)となります。(所得割については、当分の間適用し、均等額割、平等額割については、加入から2年を経過する月まで適用します。)
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
(4)未就学児の軽減
子育て世帯の経済的軽減負担を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の「均等割」について、2分の1を減額します。既に、所得の低い世帯の保険税軽減が適用されている場合は、当該軽減後「均等割」の2分の1を減額します。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870